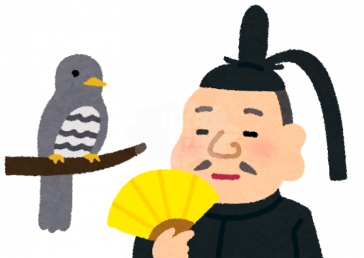加増なしは賢臣ゆえの選択か?!

「徳川四天王」の中では、もっとも低い身分から家康の最側近にまで成り上がったことで知られる榊原康政。後には、徳川秀忠の頼れる後見人として存在感を発揮しました。
康政は天下分け目の「関ヶ原の戦い」に遅参し、家康の怒りを買った秀忠のことを熱心に擁護しています。
康政の忠義に感動した秀忠は、「此度(こたび)の(康政の)心ざし、我が家の有らんかぎりは子々孫々にいたるまで、忘るる事あるまじ(『藩翰譜』)」と誓いました。
また、幕末の館林藩士・岡谷繁実が、明治初期にかけて編纂した『名将言行録』には、
「大御所(晩年の家康)の御心中を知るものは、(井伊)直政と我計(ばか)りなり、両人がことも大御所能(よ)く御存知なれども、御口外に出し給はず、誠の明君なり」
……とあり、要訳すれば「榊原康政は、自分と井伊直政だけが晩年の家康の真意を知っているし、逆に家康も自分たちのことを本当に理解しているが、言葉にしていないだけだ、本当の名君である(と言っていた)」とする逸話があります。
しかし、行動で見る限り、康政の晩年には、彼と家康との関係は冷えこんでいたと見てよいでしょう。康政、そして榊原家が、家康が関東に移住した際に与えられた10万石以上の加増を受けることはありませんでした。
これについては、家康からのさらなる加増の申し出を断ったという話もありますので決定的な原因なのかはわかりません。しかし、康政は「老臣、権を争うは亡国の兆しなり(=昔からの家臣たちが、権力争いをしていては、国が滅びるだろう)」と言って、家康たちから距離を置くようになったとも伝えられます。
家康との思い出はかつてのままに・・・

康政の最期はあっけないものでした。慶長11年(1606年)5月6日、康政は家康から与えられた上野国(現在の群馬県)の館林城で、毛嚢炎をわずらったという記録が残されています。
毛嚢炎とは俗にいう「おでき」のことを指しますが、抗生物質が存在しない当時、悪化すれば命取りになりえました。康政も運悪く、そうなってしまった一人です。
江戸時代前期に山鹿素行によって書かれた『武家事紀』では「俗伝」として、最晩年の康政の姿が次のように描かれています。
病状は悪化する一方で、康政の危篤を知った家康からの見舞いの使者が来ると、「本多正信はまだ元気なのですか?」と尋ね、康政と正信の不仲を知る使者が「もうお年ですが……」というと、康政は「あのような者を傍において、家康公はご健康でいられるのか。私などは腸が腐ってしまう」と発言したそうです。使者はしどろもどろになって退出していきました。
秀忠からも、見舞いの使者が派遣されました。康政はかねてより鼓の音色を愛し、病床に伏してからも気分の良い日は女房たちに鼓を打たせていたそうですが、秀忠からの使者に、康政は「私と共に鼓を聞いてくれないか」と申し出ました。
願いが叶えられ、鼓の音に耳を傾ける時間が終わると、康政は「まるで将軍家(=秀忠)と一緒にいられた気がします」と言い、家康や秀忠との思い出を語る一方で、秀忠には「よき世を作っていただきたい」と最後のメッセージを伝えたそうです。また、「私が死んだ後、天狗になって蘇り、お守りする」とも約束しました。
康政が亡くなったのは、それからしばらくした5月14日のことでした。享年59歳。さまざまな逸話からは、康政の気持ちが、晩年の家康からは微妙に離れてしまっていたことがうかがえるようですが、康政はかつての家康が自らの姿を水鏡に映しながら描いたという自画像を譲り受けており、その画を館林町の善導寺にわざわざ遺言して預けたという言い伝えも寺にはあります。
家康と戦場を駆け巡った日々の思い出は、康政の中で美しいままだったのでしょうか。家康の寵愛が他の家臣たちに移ったことを感じると、彼は醜い権力争いなどはせず、政治の中枢からそっと身を引くことを選んだような気がします。「四天王」の中では、もっとも精神的に成熟し、大人といえるのが榊原康政だったのかもしれません。