「明治維新の功労者」伊藤博文の国葬は、30万人もの群衆に見送られ、盛大に執り行われました。
1909(明治42)年11月5日のことです。数え年で69歳の死でした。
平均寿命が現代より短かった当時ではかなりの高齢者ですが、暗殺される直前まで伊藤は現役そのもの、衰えも知らずに仕事をこなしていました。
伊藤公狙撃さる

10月26日、伊藤は満州視察の途上、ロシアとの国境近くのハルピン駅(現在の中国・黒竜江省)のプラットホームで、暗殺されています。
清国(中国)領ハルピン駅のホームで、ロシアと清国の守備隊の閲兵儀式を見た直後のことでした。
安重根という朝鮮独立運動家の青年がピストルを発砲、三発が伊藤の胸および腹部に命中したのです。
最後の言葉は「馬鹿な奴め」とも、「やられた。三つばかり弾が入ったようだ」ともいわれますが、諸説ありますね。
伊藤の悲報はたちまちに海を越え、日本中に伝わります。
1909年10月27日当時の新聞記事抜粋伊藤公狙撃さる
伊藤公廿六日午前九時哈爾濱(ハルピン)に着しプラットホームに下るや韓人と思しき者の爲めに狙撃せられたり
それまでは彼を何かと叩き続けた各新聞なども、沈鬱な様子を見せます。
すぐに伊藤の葬儀を国葬とすることが決定し、政府はその準備に入りました。
異例の国葬

伊藤は七番目の国葬者です。
それまでは岩倉具視や島津久光、宮家の人々など、身分も功績も高い人々だけが国葬の対象者となっていた中、伊藤の国葬は「異例」の処置でした。
いくら彼が首相や貴族院議長など要職の歴任者にせよ、伊藤は下級武士の出身で、その成り上がり方は「現代の豊臣秀吉」的な扱いをうけていました。
その伊藤が国葬になったのは、明治天皇の強い意思ゆえとウワサもされたのです。
しかし天皇以下、日本全体が伊藤博文の死をいたむことになり、彼はその瞬間、名実ともに「英雄」となったのでした。

長州藩出身の伊藤と同郷で、青春時代から競い合ってきたライバル・山県有朋も「(国の仕事の途中で殉職するなど)彼の死に方は武人として、羨ましい」と語るなど、弔意を表明しました。
余談ですが、若い頃は入江すみ(すみ子)という女性をめぐって、山縣有朋と恋の対決をしたこともありました。
伊藤博文は独特の愛嬌のある人柄、容貌の持ち主でした。
なによりシャイな山縣より行動力がありました。
結果は伊藤の「勝ち」でしたが、すみとの結婚生活はあまりうまくいかず、離婚しています。
……というか、伊藤の愛妻として後に有名になる梅子との関係が、すみとの結婚生活と並行するようにはじまってしまい、梅子に妊娠が発覚した時、伊藤はすみとの結婚生活を終わらせることを決意したのでした。
梅子は伊藤を深く愛していただけでなく、伊藤という男の第一の庇護者であり、その第一のファンですらありました。
しかし伊藤が暗殺されたと聞いた時、梅子は涙ひとつ見せず、気丈に振る舞い続けたそうです。
乃木希典や東郷平八郎らも参列。大興奮した庶民は…

伊藤の遺体は11月1日に横須賀港に到着します。
横須賀線で新橋駅まで運ばれる途中に通った駅では小中学生が整列して迎え、遺族や桂太郎首相らが出迎えるという待遇を受けました(『東京毎日新聞』同年11月2日)。
会葬者が大勢くることを考え、会場は青山墓地ではなく、日比谷公園となりました。
日比谷公園内には「図書館の裏手より(略)音楽堂に対して北面八百坪の地(略)に六棟の建物を建設」するだけでなく、巨大な祭壇までもが「総て新規切り出し材」を使用し、5日の葬儀に間に合うよう、突貫工事で作られたそうです(『東京毎日新聞』1909/明治42年10月30日)。
万全の準備で迎えた葬儀当日ですが、あいにく秋雨がふりしきっていました。
それでも夜明け前から「十重二十重に人垣」が集まり、伊藤の人気の高さがうかがえたといいます。
霊南坂にあった伊藤の官邸から、彼の遺体の入った巨大な霊柩が50人もの古式ゆかしい装束姿の「雑色(ぞうしき)」たちによって背負われて運ばれていくのに先駆け、騎馬隊や、多くの軍人、国家公務員の人々、そして天皇家や各宮家から送られた「御榊」を掲げた人々などが続きました(『時事新報』同年11月5日)。

乃木希典

東郷平八郎

山本権兵衛
それら一群の後にようやく伊藤の霊柩があらわれ、その傍には乃木希典や東郷平八郎、山本権兵衛ら、「軍神」クラスの軍人たちが付き添っているのを見ると沿道の庶民たちは大興奮。
中には「パラパラと銅貨を投げて合掌する田舎の老爺(『東京毎日新聞』11月5日)」が、取り締まりの巡査に注意されるという光景も見られました。思わずお賽銭を投げてしまったようですね。
羽織袴は入場拒否?!ドレスコードが洋装になった日

日比谷公園の伊藤の葬儀に参列できるかには厳しいドレスコードがありました。
正門前には三十人余りの警察官が入場者を選別するわけですが、燕尾服を着用した上で、黒布を左腕に巻きつけ、シルクハット着用の場合は、黒羅紗を巻きつけ、襟飾りや手袋には白いものを使わなければならないなどと定められていたのです。
当時、伝統的な日本のお葬式には羽織袴姿での参列が一般的だったのですが、洋装ではない地方の名士などは入場拒否されてしまったそうな。
神式での葬儀は10時20分にはじまり、12時10分ごろまで続いたそうです。

葬儀会場の周りは、入場できない庶民たちでごったがえす一方で、なにやらイベントのような空気がただよい、伊藤の絵はがきなどが勝手に作られ、売りさばかれる始末でした。
身長の低い女性たち向けに近所の者たちがミカン箱を足台として売りつけ、少しでも公園内での伊藤の葬儀の様子が分かるようにしてやったともいいます。
現代にくらべ、娯楽が格段にすくなく、それでもエンターテインメントを欲する庶民たちにとっては、国葬は一大スペクタクル。
葬儀も見せ物のようなものだったようです。
身分の高い者ほど、庶民たちのそうした期待に答えねばならなかったのでした。
ちなみに明治天皇は「死の穢れ」を避けるという慣例上のきまりで、葬儀に参列することは出来なかったものの、伊藤の五十日祭、百日祭、一年祭の度に勅使を派遣、祭粢料と玉串を与えています。
また伊藤の死後、ほんとうに女遊びはともかく彼は蓄財には熱心ではなかったことが判明すると、明治天皇は未亡人の梅子にお金を与えたり、伊藤の子どもたちがしかるべき地位につけるようにも尽力しました。













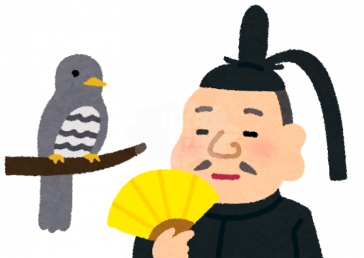













来賓には欧米系の外国人も多いと見込まれていました。
当時の欧米の喪服といえばすでに色は黒でしたので、日本人にも黒い燕尾服で来場するようにというお達しがなされたというわけです。
しかしながら、当時、喪服の色は黒ではなく白。
お棺の故人がまとっている経帷子(きょうかたびら)が白であることに合わせていたわけですが、「喪服の色=黒」に変わっていくきっかけになったのが、この明治42(1909)年11月4日の伊藤博文の葬儀(国葬)だったといわれています。
『日本ではじめて霊柩車に乗ったのは誰? <お葬式の常識の変遷>/堀江宏樹』抜粋