「亡き人の魂」に会うために…
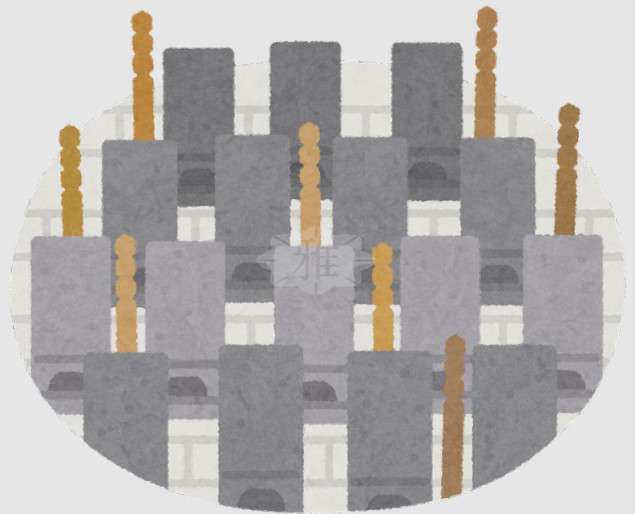
平安時代には、お墓参りの習慣がなかったとよくいわれるのですが、『源氏物語』「須磨」の巻には、光源氏が亡き父宮――桐壺院の「墓参」を行うシーンがひっそりと挟み込まれています。
光源氏は、うっかり関係した朧月夜という女性が、源氏の兄・朱雀帝に入内予定だったことから、思わぬ政治スキャンダルに巻き込まれました。「帝の女を寝取った」という罪を問われる前に京の都を出て、須磨の地に退避することになったのです。
その都落ちの旅に発つ前夜、光源氏は北山の地に眠る亡き父宮の「墓参」を試みているのです。自分を可愛がってくれていた父の魂に別れを告げると同時に、悲惨な現実を訴え、あの世から見守ってもらおうとしたのだろうと思われます。お墓に行けば、亡き人の魂に会えるという感覚が、平安時代の昔から存在していたことがうかがえるシーンですね。
このシーンは、『源氏物語』の記述を読む限り、光源氏が「御山(みやま)に参うで」る行為――つまり、火葬された桐壺帝のその遺灰、遺骨を埋めた山中を彼が歩き回ることが、「墓参」の内実だったのではないかと考えられます。
作中では、後世の天皇の陵墓のように、鳥居が建てられ、それなりに整備された場所が「墓所」だったというわけではなかったからですね。
『源氏物語』において桐壺院が亡くなったのは、一説に光源氏が23歳の時でした(「賢木」)。光源氏の「墓参」は彼が25,6歳の話ですから(「須磨」)、葬儀からまだ2~3年しか経っていないのに、山中の草木が生い茂ってしまったせいで、桐壺院の墓所がどこだったか、源氏にさえわからなくなってしまっていたという部分には興味深いものがあります。
こういうことは史実でも起こり得たのでしょうか?
ハッキリとしない埋葬場所

当時、都の郊外にあたる鳥辺野、化野、蓮台野などのエリアが葬儀と埋葬が行われる土地だとされていました。
火葬した場所に木や石の卒都婆を立てることもあるのですが、貴族の間でさえ遺灰、遺骨を土中に埋め、それですべてが完了というケースも多かったのです(庶民は火葬するだけの薪代がないので、基本的に風葬か、土葬でした)。
また、平安時代の史書などの文献において、「どこそこの場所で葬儀を行う」という記述が出てくると、それは「遺体が火葬された場所がどこそこであった」という意味になります。けっして現在のように、お寺などの施設で会葬を行ったという意味はありません。
そして、現代のように、遺骨の在り処を長い間、はっきりと示せる墓石の類の設置は稀だったので、光源氏が父宮の墓を見つけられないというのは、このような平安時代のお墓の常識を反映したものなのでしょう。
また、その場合、火葬が行われた場所をなんとなくこの辺だろうか、と訪れることを「墓参」とするしかなかったのです。江戸時代など後世に描かれた『源氏物語』の各種絵巻物では、墓石代わりの石塔や石祠に手を合わせる源氏の姿がしばしば見られますが、作中には該当する記述が登場しません。

しかし、埋葬から数年後にはもう場所がわからないお墓というのは、紫式部のような貴族階級にはありうることでしたが、さすがに天皇(正確には天皇経験者)のお墓でさえ、数年後には正確な場所がわからなくなっているというのは誇張というか、フィクションであろうと思われます。
当時の天皇、もしくは上皇や法皇が亡くなると、陰陽師が決めた然るべき日時・場所で、ご遺体を火葬にした後、遺骨を拾い上げ、然るべき寺で保管・管理するのが標準的な葬儀となりました。
しかし、明治時代以降のように国葬のような大規模な葬儀を行う習慣は当時にはまったくありません。また、遺骨を納めた寺に参詣することが、後世の「墓参り」に相当する行為だと考えられていたようですね。
紫式部の時代より、100年ほど後の時代を生きた後一条天皇の葬儀について比較的詳しく記した『類従雑例』という書物によると、天皇の遺体を火葬にした場所に、陀羅尼経を収めた石卒塔婆(石製の供養塔)などを建て、遺骨は浄土寺に運んで安置したとあります(長元9年=1036年、「五月十九日条」)。
ちなみに平安時代にも、故人が亡くなった日から数えて7日目を最初として、7日ごとに法要を行う習慣はありました。35日目の「五七の日」、49日目の「七七(なななぬか)の日」などはとくに重要な節目だったそうです。しかし、天皇、皇族の場合でも1周忌がひとつの区切りで、死後何年、何十年にわたって供養する習慣はありませんでした。

平安時代から、自分はどのように送られたいのかという遺言を残すケースは多かったようです。
紫式部が女房として仕えた藤原彰子は、彼女の夫・一条天皇から、天皇の父宮(円融天皇)の墓所に近い場所に土葬されることを希望していると、何回も聞かされていました。
彰子の父・道長も聞かされていたはずですが、彼は天皇が亡くなると、その願いを忘れたフリをして聞き届けようとしなかったようです。藤原行成の日記『権記』によると、道長は天皇を火葬にしてしまってから、土葬希望だったことを思い出したそうですよ。
道長が一条天皇たっての願いを忘れたことにしたのには、いくつか理由があったのでしょう。まず、平安時代中期において、天皇が土葬されることは珍しく、ご遺体を土葬してしまうと、通例通りに寺への納骨が難しくなることを忌避するためだったと考えられます。
そして、一条天皇にとっては長い間、「最愛の女性」だった藤原定子も火葬を拒否した事実の影響もあったのではないでしょうか。定子の遺体は霊屋という建物内に祀られ、その後は放置され、朽ちるに任せたことが知られていました。彰子の父・道長としては、愛娘のライバルだった定子と同様の葬儀を希望した一条天皇たっての願いを、意識して妨げたかったのかもしれません。
こうして一条天皇は土葬の願いもむなしく荼毘に付され、円成寺という寺で一周忌を迎えるまでの間、折に触れて「阿弥陀護摩」を修して供養をされていました。
その後、円成寺の土地にいったんは埋められたとのことです。天皇が希望していた円融天皇ゆかりの円融寺の土地に改葬されたのは、さらに3年後でした。そして現在、一条天皇の陵(みささぎ)として知られるものは、さらにその後、整備されたものなのです。


























