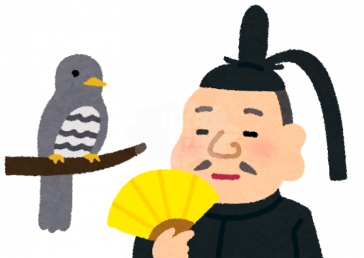今回は、豊臣秀吉を恨みながら死んでいった武将たちの辞世の歌を取り上げていきたいと思います。ご存知のとおり、豊臣秀吉は出世するごとに名前を変えていったのですが、本稿では秀吉に統一して書くことにしますね。

明智光秀「心しらぬ人は 何とも言はば いへ身をも惜まじ名をも惜まじ」
意訳すれば「誰に何を言われようと、私は正しいと思うことを貫いたまで。なんとでも言ってくれ。この上は命も、名声もどうなってもよい」とでもなるでしょうか。
江戸時代に編纂された、細川家の家譜・『永源師檀紀年録』などに収録されている明智光秀の辞世の和歌、あるいは信長を討とうと決意したときに詠まれたともいわれている歌がこちらです。

本能寺焼討之図
「本能寺の変」で信長を討ってから、わずか11日後に明智光秀は命を落としました。
味方も想定外にあつまらぬまま、高松地方から、有名な「大返し」……つまりUターンで関西まで戻ってきた秀吉軍に二倍以上の兵力で取り囲まれ、「山崎の戦い」において明智軍は討伐されてしまったのです。
戦国時代でも有数のブラック企業ならぬブラック家中だった織田家。
その魔王のような当主・信長を討った自分に味方してくれる人たちは日本中にいるはずだと踏んだ明智光秀のカンは見事に外れました。
「心しらぬ(以下略)」の歌は、恐らく辞世の歌を詠む猶予もなく絶命してしまった、明智光秀の無念な気持ちになりかわり、後世の人が詠んであげた作だともいわれています。
柴田勝家

柴田勝家「夏の夜の 夢路はかなき あとの名を 雲井にあげよ 山ほととぎす」
「夏の夜の夢は、短くはかないものですね。夜明けだ、ほととぎすが鳴いている。私の死後の名声を、雲居の高さにまでおしあげておくれ、ほととぎすよ」……くらいに訳しておきましょうか。
柴田勝家が、妻・お市の方と過ごす最後の夜が明けていくときに詠まれた歌です。
織田家の家臣団の中では新参者にすぎない豊臣秀吉に、重臣中の重臣である柴田勝家が破れることが確実になったのが、天正11(1583)年4月24日のこと。
柴田が籠もっていたのは難攻不落をうたわれた北ノ庄城でしたが、戦の開始から、わずか3日での陥落でした。
24日の午後、城の中では、最後まで共に戦った者たちが、身分を超えて歌い、飲み、踊るといった宴が催されたといいます。

お市の方
柴田は昨年秋に再婚したばかりの妻で、信長の妹のお市の方を気遣い、城の外に逃げるようにいいましたが、お市の方はそれを拒みました。
生きながらえれば、自分に執着している秀吉の側室にされることを察知していたとも言われます。
結果的にお市の連れ子である女の子3人だけが、城の外に連れ出されました(この中に、後の淀殿、お江の方などが含まれます)。
25日の早朝、豊臣秀吉の最後の総攻撃がはじまると、城の中は自害しようとする人々、彼らを介錯する人々によって血の海となりました。
柴田が妻の前で詠んだのが、この「夏の夜の(略)」の歌です。その後、柴田は夫婦で自害、城は炎上します。
しかし、これらのやりとりがキチンと残されているのは、柴田から命令された「老女(=ベテラン格の侍女)」のおかげなのです。
彼女はすべてを見聞きした後、城外に逃れ、その後も語り継ぐよう命令されていたのですね。
よほど柴田勝家が「後世の評価」を気にかけていたかがわかります……。
織田信孝

織田信孝「昔より 主を内海の 野間ならば やがて報いん 羽柴筑前」
江戸時代の軍記物『川角太閤記』などに見られる、織田信長の三男にあたる信孝の辞世の和歌です。
「私が今、死のうとしている野間は昔から、逆臣が主人を討つという因縁の土地だ。しかし逆臣にはいつか報いがある。羽柴筑前守(=秀吉)よ、呪ってやる」とでも訳しておきます。
恨みをあらわにしている点で、比較的珍しい辞世といえるでしょう。
側室女性との間に生まれた三男・信孝ですが、父・信長は彼を可愛がっていました。
一般的にはいくら父親に可愛がられていたところで、側室の生んだ男子に家の継承権はありません。
本当は正室の子で嫡男・信雄(のぶかつ)より、実は信孝のほうが数日ほど先に生まれていたのに、継承権が問題になると困るということで、信孝が三男となったという説もあるようですね。
しかし、信雄は「本能寺の変」で父・信長と同時期に戦死し、生き残った信孝を織田家の後継者に押すという流れが出来ました。
柴田勝家などが信孝を支援してくれました。信孝には願っても見ない、チャンスです。
ところがあの秀吉が、信孝の前に立ちはだかります。
秀吉は「織田家は嫡男・信雄の子で、当時まだ幼い三法師が継ぐべきだ」と主張、三法師の後見人を自分が努めると言い出したのでした。
織田家の力を秀吉が奪おうとしているのは明らかだったのですね。

賤ヶ岳大合戦の図
柴田勝家と秀吉が正面衝突した、1583年の「賤ヶ岳の戦い」の際、信孝も半・秀吉軍として蜂起しています。
しかし、想像以上にたやすく柴田が秀吉に討ち果たされてしまったため、信孝の蜂起も曖昧なことになりました。
戦後も許されることなく、自害させられることになりました。
残念ながら「昔より 主を内海の 野間ならば やがて報いん 羽柴筑前」の歌も、同時代には記録がなく、江戸時代に書かれた軍記物語というフィクションにしか見られませんが、これくらいの恨みつらみの言葉を吐いて信孝が死んでいってもおかしくはなかったと思われます。