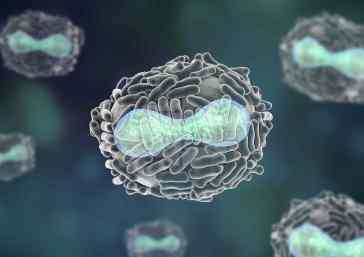世界中に感染が拡大した新型コロナウィルス。様々な型が存在し、それによって症状にはバリエーションがあるとも考えられていますが、対応のされ方にはある種の共通項があるはずです。
しかし……今から約200年ほど前の世界では、“同じ病気”でも地域によってまったく対応のされ方が違うこと、それが普通だったということには驚いてしまうでしょうか。
抗生物質が発明される以前の歴史の中で、結核は死病だと考えられていました。
すでに古代ギリシャ時代の医師ヒポクラテスによって分析された結果が残されているほど、結核は古くから人類を苦しめてきた病気でした。
痩せて青白い顔、咳や喀血。頬が赤く、目だけがギラギラと光を帯びて輝いているなどのヒポクラテスの記述は今日の目から見ても非常にリアルだとされます。
その一方で、結核は伝染病とは考えられず、家族の病気、つまり遺伝性の病であると考えられつづけたのです。
検疫を意味する「40(quantine)」の由来

しかし、17世紀末年あたりから18世紀半ばにかけ、事情は変わりました。きっかけとなったのはヴェネツィア共和国などの”事例”です。
ヴェネツィア共和国など南欧の諸都市は古くからアジアとも交易を行っていましたが、貿易の荷物とともに“病気”までもが侵入してくる事案が何度も起きています。
2020年初頭、新型コロナ感染症でも感染しているかもしれない人を、上陸させる前に検疫期間を置いていたことがありました。検疫のことをquantineと外国語表記しますが、この単語はイタリア語で「40」という数字に由来したもの。つまり防疫のため、外国からやってきた人や荷物は船から降ろさず40日間、沖合に停泊させていたという事実から来ているのです。
ちなみに結核の法定伝染病指定が行われたもっとも最初の例とされるのは1699年、イタリアのルッカ共和国であり、それが1751年にはスペインにも引き継がれていったそうです。いずれも海外との交易で富を成していたエリアの話です。何より伝染病は商業にとって死活問題でありますから。
新型コロナ対策では、“初動のミス”によって感染を爆発させてしまったイメージの強い南欧諸国ですが、18世紀の時点では商業大国として世界中とわたりあった結果に蓄えられた知識をもち、世界有数の防疫先進国でありました。
しかし、興味深いことにイタリアやスペインといった南欧以外……たとえばイギリスやフランスといった国々では「なぜか」肺結核は、ヒポクラテスの時代と変わらぬ遺伝病扱いにとどまりました。
トコロ変われば…国によって大きくかわる結核への対応

肺結核の患者であろうが、まったく行動を制限されることもなかったといいます。それどころか、肺結核になることはエリート特有の病としてひそかな憧れの対象ですらありました。
イギリス生まれのロマン派の詩人ジョン・キーツ(1795-1821)は、主治医のすすめで霧と雨の多いイギリスを離れる転地療養を実施することにしました。
しかしローマのスペイン広場近くにあった彼の下宿でキーツが亡くなると、その遺体は解剖され、彼の持ち物はすべて、それにベッドや寝具、さらには部屋の窓や天井、床板、窓枠などまでもがすべて焼却処分にされることになり、同行者を驚愕させました。実はそこまで嫌われ、恐れられていたのです。それにしてもなんという”お葬式”でしょうか!
結核はどうせ遺伝病、移るわけがない程度に「気軽」に考えていたキーツの同行者で、同じく詩人のシェリー(1792-1822)などは「ここまでするのか」と仰天したと思われます。

「ピアノの詩人」の異名を取るフレデリック・ショパン(1810-1849)も、肺結核に苦しんだ一人です。彼は病んだ肺に悪いとされる湿った冷たいフランスの冬を避けるべく、スペインのマジョルカ島に転地療養を試みますが、島民の冷たい反応に面食らいました。
フランスでは、多かれ少なかれ”エリートがかかる美しい死の病に侵された悲劇の天才音楽家”として、ときには羨望の眼差しをむけられ、はれものにさわるように扱われてきたのに、スペインではただの厄介者としてしか見られません。
つまり「転地療養だかなんだかしらないけど、病気をまきちらす迷惑なヨソモノ」としてしか接せられないのです。
とくにマジョルカ島民の反応は、イタリア・ローマなどどは比較にならぬほどに非常に厳しく、「病気のくせになんで来たんだ」といわんがばかりの冷たい対応を受けました。
宿も馬車も提供されず、「肺病患者なんて殺してしまえ!」という声がどこかから聞こえるなか、愛人(結婚はしていないが、実質的な妻)のジョルジュ・サンドと身を寄せ合うように、廃屋のような古い修道院で暮らすことになりました。

マジョルカ島デイアの街
音楽の専門書には、”肺病が悪化していたショパンにとって、冬季も温暖で乾いた気候のマジョルカ島での暮らしは想像意欲を掻き立て、名作が量産された”などと書かれていますが、たしかに避寒地で快適にくらした結果、作曲されたとはとても思えない、重苦しい旋律の曲が目立つように筆者には思われます。
一番有名なのは、「雨だれの前奏曲」(正式には『前奏曲集』第15曲「雨だれ」)ですね。
雨だれの音を聴きながらまどろんでいると、いつしか重苦しい悪夢に襲われる。雨だれの規則的なリズムが、自分を迎えにきた葬儀の行列のように夢のなかでは感じられ、目が覚める。あぁ、夢で良かった……というような音楽的展開は、ショパンが悩まされた、迫りくる死の恐怖を色濃く感じさせるものがあります。
「同じ病気」でも地域・文化によってまったく受け入れられ方が違うということは新型コロナの例でも証明ずみですが、疫病の大流行とともに人の心はおろか、社会や文化の形までもがかんたんに変化してしまうという事実とあわせて考えると、われわれが歴史に学ぶべきことは多そうです。