奇妙な符号が、歴史の中には時々存在するものです。
19世紀初頭の日本は鎖国されていましたが、それでも同時代のヨーロッパと同じように肺結核の猛威に悩ませられていました。
それだけでなく、肺結核を「美しい死の病」とする感性すら、ヨーロッパと共有していたというと驚くかもしれませんね。
文化二年(1805年)に書かれた、宮川春暉『雑病記聞』には、こんな一節が出てきます(一部表記を読みやすくしました)。
「(結核になるのは)老人・愚人・下賎の人等に稀にて、年若き、富貴の人、才力智ある人に多し」
……要するに肺結核は若いエリート様の病気である、と。
実際は、栄養失調などによる免疫力の低下で結核になるケースが圧倒的多数なのですが、日本でも同時代のヨーロッパのように、結核を理想化する傾向があったのには驚きを隠せません。
当時、日本では肺結核のことを労咳(ろうがい)などと呼びました。
「労咳は長振袖の病なり」という川柳が流行ったともいいますが、その背景には、長い袖付きの豪華な振り袖を着られるような富裕層の箱入り娘の病が結核なのだ……という認識があるのです。
一方、現代の言葉でいうインテリの若い男がなってしまう病という認識もあったそうです。たとえばこんな川柳が……。
「労咳の母は近所のドラを褒め」
ドラ=ドラ息子の略ですね。つまり「ウチの子、勉強はよく出来たけど結核になっちゃったじゃない。お宅のお坊ちゃま、ずっとお元気そうで羨ましいわぁ~」という手合のマウンティング行為だとも取れますが。
ちなみに結核になっても、江戸時代の人々はあっけらかんとしたもので、あることをすれば「治る」病という印象があったのは興味深く思われます。
結核の特効薬は薬にあらず

結核の特効薬とされたのは、なんと「恋」でした。
箱入り娘・箱入り息子の病気が結核だといわれるのも、「大事にしすぎて世間の風にも当てようとないから、色白になって痩せてしまうのだよ」「恋でもさせて意識を外に向けさせなよ」という理屈なのですが、「結核だから痩せた」とは考えないところが、妙にポジティブ。ある意味、微笑ましくはありませんか?
結核は誰かに伝染させうる病気なので、そこまで楽観視するのも本当はダメなのですが、現代日本の医療でさえ全ての病が治せるわけではありません。
現在でも根治できる病はむしろ少数であり、「死」まで共存していくべき存在だったりもするのですから、江戸人のポジティブさにはある種の救いを感じる筆者なのでした。
巷間の認識は「贅沢病」から「社会病」へ

しかし、江戸時代が「文明開化」によって終わると、近代医学の知識が日本にも流入してきます。肺結核という病気のイメージはガラリと変わりました。これまでのように上流階級の箱入り娘・息子などがなる「贅沢病」の扱いから、社会病として肺結核のイメージはじわじわと強くなっていきます。
その一方で、悲惨な結核感染現場から目を背けるためか、結核にロマンを求める人々もいなくなりませんでした。
本場ヨーロッパのロマン主義の描く肺結核の「魅力」に取り憑かれる芸術家も出てきます。そしてこれが大人気になるのですね。
明治31年(1897年)からその翌年にかけて書かれ、大ヒット作となった徳富蘆花(1868-1927)の小説『不如帰(ほととぎす)』は、日本に本場ヨーロッパのロマン主義的な肺結核のイメージを根付かせた作品でした。
タイトルにもなったホトトギスは、血を吐くまで泣き続けるという「伝説」を日本では古来から担わせられた鳥です。懸命に最期まで生き抜こうとする肺結核のヒロイン・浪子の姿が投影されているのです。
しかし、興味深いことにこの作品の中で、浪子の心身をむしばむ結核は、上流層特有の遺伝性の病ということに「なぜか」なっているのです。どうせ治せない病であれば、少しでも魅力的に思われるように描いたほうがいい……そういう徳富蘆花の「演出」があったのかもしれませんね。
ドイツの細菌学者ロベルト・コッホ(1843―1910)が結核菌を発見したのが1882年のこと。それから約15年以上が経過しているのに、「どうして?」と思ってしまいがちですが、肺結核に効果のある抗生物質が、当時はまだ発明されてはいません。
実際、明治末の医師たちが、肺結核の薬として処方していたのはクレオソートという薬剤が多かったといいますが、これは現在では胃腸薬として知られる薬。
クレオソートは現在でも市販薬として手に入れることができまして、その一番有名な銘柄は「正露丸」です。たしかに正露丸を飲んで肺結核を治そうというのは、なかなか遠大な計画だったでしょう。
いずれにせよ、なぜ結核が洋の東西を問わず、理想化される病、そして理想的な死をもたらす存在にさえなっていったかは奇妙な問題です。
昨今の文学が「力」を失ったのは、肺結核という主題がアクチュアリティを失ったからだという江藤淳や吉村昭の説もあるほどですが、ある種の「病」、そしてその結果の「死」が創作のパワーとなり、ひとつの時代を象徴する要素でさえあったことは非常に興味深く思われるのでした。

歴史エッセイスト・作家 堀江 宏樹
江藤淳と吉村昭いわく、肺結核と戦争という二大要素が文学に「力」を与えていた、と。しかし肺結核も戦争もともに「死」をもたらすものであり、人類史上もっとも文学が隆盛したとされる19世紀ー20世紀、文学最大のテーマは「死」だったということになる。
まぁ、これは肺結核がどれだけ多くの人びとを苦しめていたか、ということに他ならないのですが……。













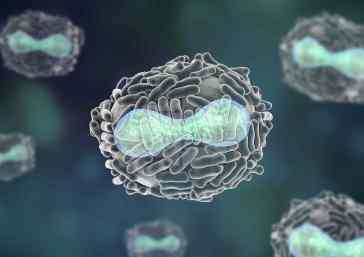
歴史エッセイスト・作家 堀江 宏樹
恋がダメでも、他の治療法もありました。黒猫を膝に抱くだけでも肺結核にはよいといわれていたそうです。