現代では、中江兆民の名前は知る人ぞ知るという程度の知名度でしょうか。
雑学好きのひとには、日本で最初に「告別式」をお葬式代わりに行った人として知られているかもしれません。
日本のジャン・ジャック・ルソー

1847(弘化4)年に、高知で足軽の子として生まれた中江ですが、幼少期から学問、とくに外国語の才能に秀でたものを示していました。
当時の日本では数少ない有識者に教わったフランス語のレベルは高く、彼は日本初の国際派ジャーナリストの一人でした。
また「日本のジャン・ジャック・ルソー」ともいわれるように、西洋の思想哲学を体系的に学んだ最初期の日本人でもありました。
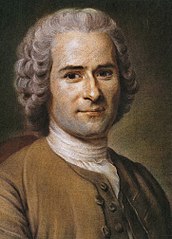
18世紀フランスの政治哲学者
しかし、この手の天才肌の人物にありがちなように、中江も多少、変わったところがありました。
「肉体を外にして霊魂の決してあるべきはずはなし」と公言する中江は完全な無宗教主義者でしたから、お付き合いとしての葬儀に参列することはしても、そこで変わったことを平気でやってのけるのです。
ある時、友人が亡くなったので、中江もお悔やみに出かけることになりました。中江は友人の霊前にぬかづいて、弔意を表しました。
「なんだ、普通じゃないか」と思ったら甘いのです。
中江は未亡人にお悔やみの言葉をかけた直後に「ちょっと二円(=数万円)ほど貸してくれないか」と持ちかけるのです。
未亡人は一瞬、「こんな時に」とムッとするのですが、お金を渡してやりました。すると中江は礼の言葉もなく、未亡人にその金をうやうやしく差し出し、香典代わりにした(『明治人物逸話辞典』)」とかなんとか。
一体、彼が何を考えてそんな奇行に走ったかはわかりませんが……。
余命一年半…迫り来る死と戦う日々

そんな中江ですが、晩年は病気による痛みを抱え、迫り来る死と戦う日々を過ごすことになりました。
1901(明治34)年の春、中江は東京から大阪に出張中でした。
しかし、しつこく続く喉の痛みの本当の原因を知るため、医者の診察をうけざるを得なくなったのです。結果は末期の咽頭がんでした。
5月後半には手術が行われます。
しかし余命は「一年半くらい」と大阪の医者からいわれてしまう中江ですが、「一年とは余の為めには寿命の豊年なり」、つまり「一年も寿命があるのなら、本当にありがたい」と来るべき死に先駆け、自分が最後に思うことなどを、『一年有半』というタイトルで書き記し始めたのです。
副題を「生前の遺稿」とする、哲学的エッセイで7月11日に第一部、7月18日に第二部、8月3日に第三部をすごい勢いで書き上げ、9月2日に博文館という出版社から単行本が出版されました。
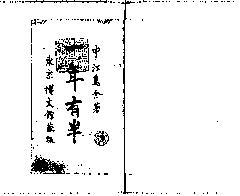
この『一年有半』は発売から1年あまりのうちに20万部が販売されるという大ベストセラーとなったのです。
本の発売直後に東京に戻る中江ですが、東京帝大医学部の医者には「寿命はいくばくも残されていない」と告げられました。
すると、『続一年有半』という続編を、わずか20日あまりで書き上げたのです。
今度の副題は「一名無神無霊魂」というもので、「断じて無仏、無神、無精魂、即ち単純なる物質的学説を主張する」といいきっています。
魂などは肉体死んだらそれで終わりだし、死後の世界などもない。だから葬式をどうすると考えることも「笑止千万」。
だから自分は葬式をしない。遺体の埋葬だけしてくれ、と言い残したのでした。
弟子の幸徳秋水によると、中江は飲み食いはおろか、寝ることすらできないほどの痛みを抱えながら、それを「麻痺剤」を使って散らして執筆を続けたそうです。
しかし『一年有半』の文章は平明で、ときどきユーモアすら交っています。とても凄まじい苦しみを抱えた人の文には読めないのですね。
恐るべき精神力というべきでしょうか。
日本初の「告別式」を取り仕切った板垣退助

中江が亡くなったのは同年12月13日でした。
余命一年半といわれていたのに、その半分程度も生きられなかったところに、文字通り、生命を燃やして彼が執筆活動を続けたことがあらわれているようです。
中江の遺言は、次の二行だけでした。
「第一 遺骸は解剖に附する事
第二 葬式は行わざる事」
これらはすべて遺言のとおりに運びました。
そして無神論にして無宗教主義者の中江の遺言どおり、お葬式のかわりに、行われることになったのが「告別式」だったのです。
現在ではお葬式のある段階としてお通夜などと告別式が同一視されがちですが、元来、告別式とは無宗教の「お別れの会」的なイベントでした。彼の告別式に参列したのは千人以上もの人々でした。
中江の棺は小石川(現在の文京区)の自宅から、告別式会場の青山墓地(現在の港区)までは霊柩人力車に載せられて運ばれました。
また、中江の告別式をとりしきってくれたのは、彼と同じく高知の土佐藩出身だった板垣退助らでした。
『一年有半』の中で、もうすぐ未亡人になるであろう自分の愛妻に冗談めかして「お前も四十を過ぎているから再婚なんかできないだろう。私と一緒に死のうか」などと話をした、と書いていましたが、やはり自分が死んだあとの家族のことは心配だったようです。
中江は死後の世界も絶対に信じていないのですから、「天国でまた会おうね」「来世も夫婦になろう」なんて情緒的なことも言えないわけですし、遺族もよけいにつらい部分はあったかもしれません。
だからこそ、中江は旧知の友人らに、自分の死を悼む詩などを告別式で朗読してもらったようです。
そして、それが自分の遺族にとっての慰みになるかもしれないという理由で告別式の開催だけには賛成していたそうです。不器用な人だったのかもしれない、と思うのは筆者だけでしょうか……?













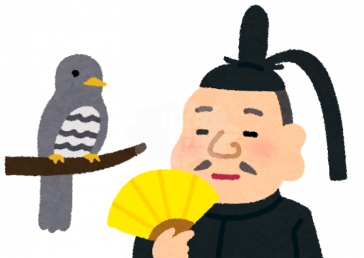













漢字では「額付く」と書く。丁寧に礼拝することを意味します。