| アントン・ウェーベルン (オーストリアの作曲家、1883年 - 1945年 享年62歳) | |
| 死因 | 射殺 |
|---|---|
20世紀前半を代表する前衛作曲家アントン・ウェーベルン。
ドイツ語読みでは「アントン・ヴェーベルン」ですが、より一般的な名称を今回は採用しました。
ウェーベルンは音楽史の中では「十二音技法」といわれる非常に革新的な作曲法で作品を残したことで有名です。
十二音技法とはなんぞや?

平均律の12種の音を均等に用いた(作曲)作法(『世界大百科事典』)……といっても、よくわからないと思います。
そこで、ごく単純化した説明をここでは行います。
十二音技法とそれ以外の技法で作曲された音楽では、ドレミファソラシドの音の使い方が「まったく別」になります。
そして、十二音技法を使った音楽には、ハ長調とか、ニ短調といった調性というものがありません。
たとえばハ長調という調性をもちいた調性音楽は「ド」ではじまり、「ド」で終わるのが通例です。
つまりドが主音であり、主音とはいわば主(あるじ)の音なのです。
主音こそが調性音楽ではもっとも「重視される」という「お約束」がありました。
この「お約束」がなければ、おなじみのコード進行なども使えなくなります。
たとえばドミソ、ドファラ、シレソ、ドミソ……などの「流れ」の一切が消えてなくなるわけです。
十二音技法では、その手の主音の縛りがありませんので、音階にある十二の音すべてが平等に扱われます。
そして調性がないぶん、非常に耳慣れない、斬新かつ不安定で混沌とした響き……つまり不協和音に満ちた音楽が生まれるわけです。
なぜそんなめんどくさいことまでして、リスナーが少なそうな音楽を作ろうとしたのかと読者は思うでしょうが、十二音技法が生まれるまでのロマン派の音楽では芸術家のインスピレーションこそ命とされていました。
音楽理論より、曖昧で、気まぐれなインスピレーションこそが重視されすぎる秩序なきロマン派音楽の世界にヘキエキとする感性の持ち主が、19世紀末~20世紀初頭に次々と生まれていったのです。
そして……不協和音にみちた音楽を、比較的かんたんに作ることができる手段としても十二音技法は有能でした。
そこまでして不協和音に満ちた音楽に需要が?……と思うでしょうが、不協和音=不安や苦悩の象徴です。
十二音技法が生まれた19世紀末ー20世紀初頭には、ヨーロッパ全土に不安の雲が立ち込めはじめていました。
各地で革命が起き、ロシアやオーストリアなどでは王朝が倒れ、さらには第一次世界大戦まで起きてしまいました。
こうして不安と激動の時代・20世紀前半を象徴するような音楽をつくりだすべく、ウィーン生まれの作曲家アルノルト・シェーンベルクによって、十二音技法は発明され、弟子のアルバン・ベルク、アントン・ウェーベルンの手によって発展していったのでした。
しかし、プロの音楽家でも十二音技法を理解する人は希少でした。
そもそも、メロディらしいメロディもないので暗譜するのが極めて難しいだけでなく音域的にもムリがあることが多く、たとえば1940年代まで、ウェーベルンの歌曲を原キーで歌えるのは、ベサニー・ビアズリーというアメリカのソプラノ歌手くらいしかいなかったそうです(チャールズ・ローゼン『ピアノ・ノート』)。
自分の歌曲を実際に聴くということが生前のウェーベルンの場合、ほぼ不可能だったということですね。
「十二音技法」は常識はずれの前衛作曲家でも理解困難だった?

グスタフ・マーラー
シェーンベルクやウェーベルン、そしてベルクといった「新ウィーン楽派」の面々は、ギネスブックも認定する「世界最長の交響曲」を作ったことで知られるグスタフ・マーラーを大先輩として慕っていました(『交響曲 第三番』)。
マーラーも常識はずれの前衛作曲家でほとんどの作品が聴衆に理解されず、悔し紛れに「いつか私の時代がくる」などと言っていましたが、その彼ですら十二音技法を使った音楽は理解できていませんでした。
前衛作曲家として生き続けるのは、容易なことではありませんでした。
ヒトラーとナチ党が台頭したドイツ・オーストリアでは、「新ウィーン楽派」の作品は退廃音楽として目の敵にされました。
シェーンベルクがスペインのバルセロナに亡命したのは1938年のこと。
弟子のウェーベルンは、師匠のオーケストラのための作品『映画の一場面への伴奏音楽(原題 Begleitungsmusik zu einer Lichtspielszene)』を、バルセロナでの現代音楽祭で演奏したいと申し出ました。師匠を応援したいという気持ちがあったのでしょう。
ところがシェーンベルクは、ウェーベルンのたのみを断りました。
「あの酷い音楽を聴いたら、友人たちはなんて思うだろう」が理由でした。
「友人」とは、シェーンベルクが入っていたバルセロナのテニスサークルの人々のことです。
身内にしかうけない変な曲を書いていて、売れない作曲家だと自分のことを思われたくなかったと当人が認めているのだから、もうなんともいえません。
こうして、「誰トク」のお荷物になってしまった感のある十二音技法なのですが、新ウィーン楽派の面々が亡くなった後も、「現代音楽」の後継作曲家たちの手によって進化を続けていきました。
「新ウィーン楽派」の中でも、アントン・ウェーベルンのファンはさらに少ないのですね。極論すると、現代日本ではモーツァルトの1万分の1も聴かれていないと思われます。
極端に短い曲が多く(それゆえ「結晶のような響き」などともいわれますが)、全作品数でもCD6枚分と寡作。
そもそも不協和音多用で、メロディらしいメロディも拒否した前衛的すぎる作風で人気が出ませんでした。救いは演奏時間短いこと、くらいでしょうか。
それでも若い頃はよかったのです。
ウェーベルン家は広大な領地を有するオーストリア貴族の家系でしたから。
前衛的過ぎるがゆえに「退廃芸術」の烙印を押されるハメに

しかし・・・・・・時代が悪かった。
ヒトラー率いるナチス・ドイツによってオーストリアが併合されたあげく、彼の領地収入は途絶えました。
さらに困ったことに、前衛的過ぎる作風をヒトラーに「退廃芸術」呼ばわりされてしまい、ウェーベルンは音楽家としても完全に食べていけなくなったのです。
ただし、娘婿がヒトラーに仕えるナチス親衛隊の一員だったので戦争中はなんとか・・・・・・。
それも戦後は最悪の結果となりました。
ナチスの親族を持ってしまったウェーベルンは、今度はアメリカ兵から監視される立場となりました。
そしてベランダでタバコを吸おうと火をつけた瞬間に、「パーン」。
銃声が鳴り響き、ウェーベルンは倒れました。
「彼が闇取引の合図をしているように見えた」という言いがかりで、アメリカ兵に銃殺されてしまったのです。
あまりに悲しい「ホタル族」の死でした。













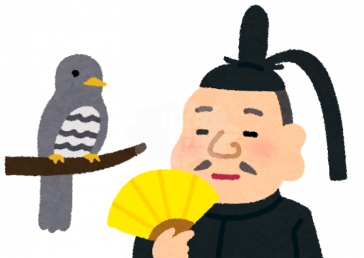













歴史エッセイスト・作家 堀江 宏樹
作曲者本人に酷い音楽といわれた『映画の~』ですが、興味のある方は原題でユーチューブかなんかで検索してみてください。白黒時代のホラー映画のワンシーンみたいな感じですね。