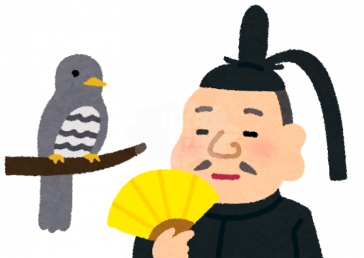夏目漱石が亡くなったのは1916年(大正5年)12月9日のことでした。
奇妙に思われるでしょうが、漱石は自分が死んだら、お棺の傍らでみんなに「万歳」してもらいたいと言っていました。
彼の弟子・岡栄一郎のエッセイ『夏目先生の追憶』にはこんな記述も出てきます。
「己(=私)が天命尽くる期がきたら、己は喜んで死を迎える。死は己に取って慰楽の境地である(略)己の柩の前に集って『万歳』を叫んで貰いたい」
また、死の約二年ほど前に書かれた、弟子の林原耕三あての手紙でも
「(私が)死んだら皆に柩の前で万歳を唱えてもらいたいと本当に思っている(略)。死んでも自分はある、しかも本来の自分には死んで始めて還れるのだと考えている」(大正3年11月14日付け)。
1910(明治43)年の夏、伊豆の修禅寺温泉の旅館で漱石は約800グラムも大量吐血し(!)、何日も生死の境を彷徨いました。
その時、彼は幽体離脱を経験しているんですね。
感想をまとめると「楽しかった」そうですが、この時のことを思い出して書かれたのが、1915年(大正4年)『硝子戸の中(うち)』というエッセイですが、「余は(臨死体験である幽体離脱中に)余の個性を失った。余の意識を失った。ただ失った事だけが明白なばかりである。どうして幽霊となれよう」と書いています。
つまり、霊魂など信じていない、と。
親しい弟子に語る言葉や手紙の中では、霊魂を認めているのに、公衆にむけて語りかけるエッセイの中では「死んだら意識が途切れるだけだから、霊魂なんてものはないんだよ(筆者要約)とドライな感想を述べているのでした。
プライベートでは情緒的な漱石と、オフィシャルではクールな漱石という対照的な二つの顔が、彼の中に存在していたように筆者には思われます。
当時の文学者、小説家といえば先進的な知識人の鑑たるべきですし、そもそも漱石はイギリスに国費留学している社会のエリートです。
そんな自分が霊魂(という眼にみえないもの)を信じていると公言することは、立場的にも許されないと感じていたのでしょうか。
漱石の死生観にうかがえる、本音と建前のギャップは、彼の生きにくさを象徴しているように筆者には思われます。
現在も東大博物館に残る漱石の「脳みそ」

晩年は病気がちだった漱石がついに危篤に陥ったのが、1916(大正5)年12月9日の午前2時頃でした。
しかし朝になっても「いよいよ……」という様子はなかったので、子どもたちは学校に向かわせられます。
気晴らしとして漱石は小説を書き始めたのに、その執筆はいつしか大きなストレスとなり、持病の胃潰瘍の症状は重くなる一方でした。
それゆえ妻の鏡子や子どもたちに癇癪を爆発させることも度々あったのですが、家族たちから漱石は愛されていました。
子どもたちは父親を心配しながらも家から出かけますが、次女の恒子と四女の愛子は通学路でただならぬ予感に襲われ、自宅に戻ってきました。
長女の筆子は学校に迎えに出した人力車が途中で転倒するも、這って中から出て、帰宅しています。
一足早くに帰宅した次女と四女が涙を抑えられず、漱石の枕元で泣いてしまうと、漱石は「もう泣いてもいいんだよ」とやさしく言ったそうです。
これが彼の最期の言葉ともいいますね。午後7時前、漱石は息を引き取りました。数えで50歳の死でした。
漱石自身の強い遺志のひとつに「自分の遺体を解剖してほしい」がありました。
かつて五女が亡くなったときに解剖をしなかったので、何が娘の死因となったかが分からなかったことが夫婦の心残りになっていたそうです。
東京帝国大学医学部にて漱石の死の翌日、12月10日午後1時40分から行われた解剖では、胃と脳が調査されました。漱石の脳は現在も東大の博物館に標本として保存されているのは、この時に夏目家から寄付されたからです。
彼の脳ですが、平均より多少重たい程度だったそうですよ。
死後も「家」と「個」の狭間で翻弄された漱石

11日には通夜、12日の早朝から葬儀がはじまり、7時半から臨済宗の読経がなされたそうです。夏目家の菩提寺は浄土真宗でしたが、生前の漱石は鏡子に「禅宗のお経なら聞いてもいい」などと言っていたため、臨済宗での葬儀となったそうです。
ところが、漱石のお棺の様子を見た、弟子の芥川龍之介は「細くきざんだ紙に南無阿弥陀仏書いたのが、雪のようにふりまいてある(『葬儀記』)」と証言しています。
これは浄土真宗の流儀です。夏目家の伝統と漱石本人の意思などが複雑に絡みあった葬儀でした。
さすがに漱石のお葬式で「万歳」コールがおきることはありませんでした。
漱石の遺体に対面した芥川龍之介は
「輪廓(りんかく)は、生前と少しもちがわない。
が、どこかようすがちがう。(略)僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。『これは先生じゃない』そんな気が、強くした(『葬儀記』)」
と書いています。
漱石の魂はすでに黄泉の国に旅立ってしまった後だったのでしょう。
その後、漱石の遺体は落合火葬場で火葬され、雑司ヶ谷に漱石の代に新設された夏目家墓地に埋葬されました。
葬列を組むことを漱石が嫌がっていたので、棺の移動には自動車や馬車が使われたそうです。