「えらい人」だけれど、その「えらさ」を実感する機会がない……そういう人は歴史を通じていっぱいいますね。

二葉亭四迷
独断と偏見でいえば、明治の文学者・二葉亭四迷(本名:長谷川辰之助)もそのうちの一人ではないでしょうか。
今回は彼のちょっと残念な人生と死についてお話ししましょう。
坪内逍遥が提唱した「言文一致」をさらに洗練

1864年4月4日(元治元年2月28日)、江戸の市ヶ谷で生まれた彼は、外交官となることを目指し、1881(明治14)年、東京外国語学校(現東京外国語大学)露語科に進学します。
語学の才能はたしかにありました。
しかし、教授陣との軋轢が原因で学校を途中退学してしまうのです。
1883(明治16)年から1885(明治18)年末までを、専修学校(現在の専修大学)で学んだ末に小説家を志し、文学者・坪内逍遙の門を叩きました。
坪内逍遙と二葉亭四迷の名前もセットで、高校の国語のテスト用に「言文一致」という単語と覚えた程度という読者が多いかもしれません。
日本近代文学史において「言文一致」は画期的なスタイルでした。
今、読者のみなさまが読んでいる、筆者のような語り口調の文体が「言文一致」です。
それまでは何もかも漢文を読み下したような調子で、たとえばどんな痴話喧嘩のシーンですら格調高く文章表現されがちだったのです。
「嗚呼、わが乙女の純潔を君、踏みにじり給ふか!」とか、そういう感じですね。
言文一致は坪内逍遙が提唱しはじめた概念なのですが、坪内の作品は必ずしも言文一致していない場合が多かったのです。
坪内の弟子・二葉亭四迷は、言文一致のスタイルの洗練に努めました。
「くたばってしまえ」がペンネームの語源?

新編浮雲 第1編
二葉亭四迷著/出版:金港堂
国会図書館デジタルコンテンツ
1887(明治20)年から約2年をかけ、二葉亭四迷は『浮雲』という小説を発表します。
自意識ばかりを肥大化させたエリートが、実社会の会社組織にまるで対応できず、落ちぶれてしまうというような現代でも通用する「リアル」を備えた小説で、大きな話題を呼びました。
明治も中期となれば、日本各地の大学を卒業したエリートたちを待っているのは多くの場合、失望だけでした。
「身の油に根気の心(しん)を浸し、眠い眼を睡(ね)ずして得た学力を、こんなはかない馬鹿気た事に使うのか(二葉亭四迷『浮雲』)」、というような仕事にしか、就けませんでしたからね。
1887(明治20)年頃にはすでに大学卒業者の数は(現代と比べればさすがに少ないとはいえ)大都市圏においては増加傾向にあり、大学を出たからといって、それだけで良い仕事に就けるわけではなくなっていたのでした。
『浮雲』という小説を執筆、刊行する際、二葉亭四迷は自作のクオリティが低いのではないかと思い始めます。
彼が取った解決策は、なんと師匠・坪内逍遙の名前で本を出すこと。
『浮雲』は好評を得ますが、坪内の名前を使ったせいで、師に印税の半分を収めねばならなくなりました。
そんな自分自身を罵る言葉としての「くたばってしまえ」が「二葉亭四迷」のペンネームになったのです(二葉亭四迷『予が半生の懺悔』)。
天職を探し続けた二葉亭四迷

Ximeg [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons
二葉亭四迷はその後、20年あまりも小説執筆から遠ざかります。
その間に彼は役人に転身したり、語学堪能な才能をいかして大学の外国語教師(ロシア語)になったりしています。
どの職場でもそれなり以上の成果をのこすものの、彼自身がどこか満足できず、仕事はころころ変わるのでした。
「男子一生の仕事」、「天職」を見つけたいという強迫観念に支配されていたのかもしれません。
その後、新聞小説に力を入れていた東京朝日新聞に勧誘されて入社。
月給百円(現在の価値で約百万円)を貰いながら小説執筆をイヤイヤながら再開するのでした。
しかし、そのイヤイヤっぷりが上司に伝わったのでしょうか。執筆再開からわずか数年後、1908(明治41)年に東京朝日新聞の特派員として、そして日露文化交流の架け橋となるべく、ロシアに赴任しています。
ロシア到着からしばらくした翌年二月、厳しい寒さの中、何を考えていたのでしょうか。
ロシア皇帝の親族にあたるウラジーミル大公の葬列を野外で見送っていた二葉亭は、雪中に卒倒してしまったのでした。
その時は、ただの風邪でした。
不治の病肺結核に

しかし二葉亭はロシアにわたってからは不眠症に悩ませられ、神経衰弱を起こしており、体力が落ちていました。
風邪をこじらせた二葉亭は肺炎と肺結核を併発、死病を得た彼は帰国をよぎなくされます。
厳冬のシベリア経由の日本帰国は身体にこたえるという理由でやめ、ロンドンまでいったん出て、スエズ運河を経由、そこからインドや東南アジア近海を通って帰国するという手段を選んだのですが……これが凶と出ました。
要するに暑いので、肺結核の症状が一気に進み、スリランカのコロンボ港に入る5月には危篤になってしまったのです。
律儀な二葉亭は毎日自分の体温を記録しつづけていましたが(通称『体温日記』)、死が刻々と迫っているのは自分でもわかったでしょうね。
5月10日、ベンガル湾上にて彼はついに亡くなってしまいます。
本人は遺体を海に流す「水葬」でかまわないと遺言していたのですが、周囲の判断で防腐処置を施された上、納棺され、船客たちが通夜を行ってくれました。
5月13日には、日本人僧侶が滞在しているシンガポールに到着、読経の末に荼毘に付されたそうです。
家族の待つ新橋駅に汽車で遺骨が戻ったのは、30日午前9時のこと。
二葉亭四迷は身長177㎝で、成人男子の平均身長が150㎝代の当時としては大男でした。
その彼が遺骨となって「一尺四方形(30㎝の正方形)」の棺に収められているのを見たとたん、二葉亭の老母は遺骨が載せられていた一等車の扉に顔を押し当てて泣き始めたそうです。
葬儀は6月2日、巣鴨の染井墓地にて神葬で行われ、数百人が参列したといいます。
5,60名のみが埋葬地まで歩いて向かいました。
彼の墓標をペンネーム「二葉亭四迷」とするか、本名「長谷川辰之助」にするかで、墓標の揮毫をまかせられた明治期のジャーナリスト・池辺三山は大いに迷います。
小説家としての自分に、二葉亭四迷は最期まで自身をもてずじまいで、二葉亭の名前も嫌っていたのを知っていたからです。
しかし結局、知名度が優先され、墓標には「二葉亭四迷の墓」と刻まれることになったのでした。
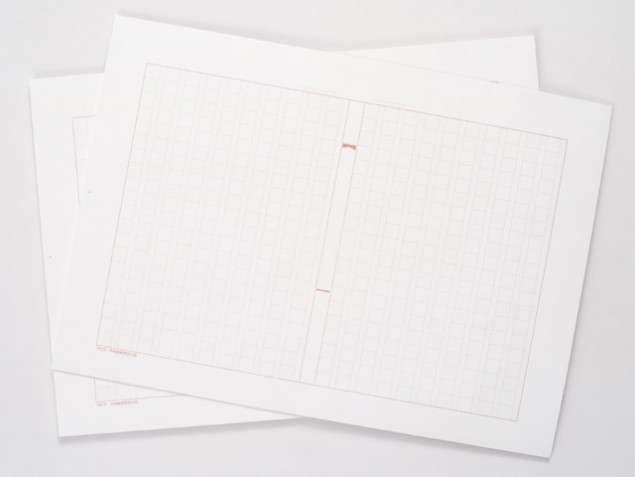












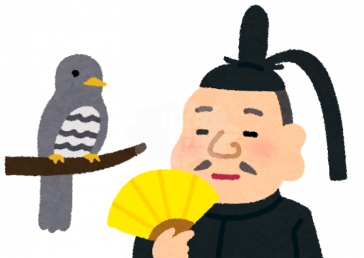













歴史エッセイスト・作家 堀江 宏樹
もともと二葉亭は、海上で死んだら、水葬すること(海に遺体を流すこと)で良いとしていましたが、船の人々はそれをあえて行いませんでした。
あまりにそれでは残念だ、むごすぎるなどと思ったのではないかと推察されます。
その結果、彼の遺体はシンガポールで、仏教の僧侶によって荼毘に付されました。
しかし、通常、荼毘に付された遺体であれば骨壷に保管され、布製のケースがかけられ、持ち帰られるのが一般的だと思われます。
しかしながら、当該箇所については「一尺四方形(30㎝の正方形)の柩」(『東京毎日新聞』記事)、またその他の文献にも「小さな白木の箱」などとあり、骨壷ケースというより、遺体が収められたお棺を模した見た目にしていたことを不思議に思われるかもしれません。
推察するに、
・本来は遺体のままで帰国させたかった
・しかし当時の腐敗処理技術、持ち込めるまでの時間、遺体の大きさなどの課題があったので火葬にせざるをえなかった。
・荼毘には付したものの、せめては形式上として本来荼毘に付する前の状態を模する形、つまり「棺」にいれた状態に近づけようとした。
これらが、30センチ四方という特殊な柩が用いられた理由だと考えてよいでしょう。
遺族の気持ちを慮って…ということも確実にあったと思いますが、なぜそこまでしなくてはならなかったかというと、二葉亭の葬儀が神道式の葬儀(神葬)で行われたからでしょう。
シンガポールで火葬されたのは、あくまで「しようがなかったから」ということ。
というのも、明治維新を支持する層には神葬を希望する率が高かったのです。
そして明治初期、政府は神葬において遺体を火葬することを「仏教風」だとして禁止すらしていたのです。
二葉亭が亡くなった明治42年時点では、神葬であっても、遺体を火葬にすることも「可」となっていたのですが(土葬には、広い墓所を確保するだけの経済力が必要だったので)、本来なら「由緒ただしく、土葬にしたかった」という希望が二葉亭やその家族にはあったのかもしれませんね。